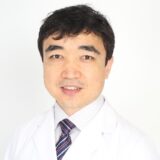監修医師:
村上 知彦(薬院ひ尿器科医院)
腎梗塞の概要
腎梗塞(じんこうそく)は、腎臓の動脈が血栓(血液のかたまり)で詰まることで血流不足をきたし、機能不全に陥る疾患です。
腎梗塞の発症率は人口100万人あたり数人程度で、比較的まれな疾患です。心臓疾患との関連性が高い疾患とされ、心房細動などの既往歴がある人に発症が多く見られます。腎疾患などのその他の既往歴や外傷を原因疾患とするケースもあるとされています。
腎梗塞の主な症状として、突然現れる背部痛や腹痛、発熱、嘔吐、血尿などが挙げられますが、無症状で経過することもあります。
痛みなどの症状からだけでは、胃腸炎や胆のう炎、尿路結石などの疾患と鑑別が難しく、診断に至るまでに時間を要することがあります。
腎梗塞の治療には、保存的治療やカテーテル治療、外科的治療などがあります。
発症から治療までの時間や合併症の有無、健康状態などを考慮して、適切な治療法が選択されます。
腎梗塞を発症すると、腎組織の壊死により腎臓の機能が回復しないケースが少なくありません。重症な腎梗塞や両側に発症した腎梗塞は、急激な機能低下により急性腎不全などの深刻な病態に移行し、透析治療が必要になるケースもあります。
このため腎梗塞の治療では、早期の診断と適切な治療が必要です。

腎梗塞の原因
腎梗塞は、血流不足をもたらす原因によって血栓性(腎動脈そのものに異常をきたした状態)と塞栓性(他の臓器にできた血栓が腎動脈に詰まった状態)の二つに大別されます。
血栓性の腎梗塞をきたす要因には、腎動脈瘤、動脈硬化などの血管の病気や、血液が固まりやすくなる疾患、外傷による腹部の強打などがあります。
塞栓性の腎梗塞をきたす要因には、心房細動や心臓弁膜症、心筋梗塞などの心臓疾患や血管内のカテーテル操作の影響によるものなどがあります。
腎梗塞の前兆や初期症状について
腎梗塞では、さまざまな症状が見られます。
主な症状として、急激な背部痛(腰や背中の痛み)、激しい腹痛、発熱、吐き気、嘔吐、血尿などが挙げられます。
腹痛では脇腹の痛みを訴える場合が多いですが、上腹部や下腹部などの痛みを訴える場合もあります。
ただし、これらの症状は胃腸炎や胆嚢炎、尿路結石、腎盂腎炎などと似ているため、腎梗塞にだけ特徴的な症状というものは捉えづらく、発見が難しかったり、治療の開始が遅れたりする場合が多い疾患とされています。
さらに、腎梗塞を発症していても自覚症状に乏しいケースもあることが知られています。
腎梗塞の検査・診断
腎梗塞の診断では、主に血液検査や尿検査、画像検査(造影CT検査、核医学検査など)、心電図検査が選択されます。
血液検査では、LD(アイソザイムⅠ,Ⅱ)という酵素の値や白血球数などの変化を確認します。
腎梗塞を発症すると、一般的にLDと白血球数の上昇がみられます。
尿検査では血尿やタンパク尿の有無を確認します。
造影CT検査の所見は腎梗塞の確定診断に有効です。
とくに血液検査でLDの上昇や血尿、タンパク尿が見られた場合には、腎梗塞を発症している可能性が高く、造影CT検査がおこわれるケースが多いです。
造影剤が使用できない場合は、核医学検査が選択される場合もあります。
心電図検査は、腎梗塞のリスクが高い心房細動などの疾患がないか確認する目的でおこなわれます。
腎梗塞の治療
腎梗塞の治療には、保存的治療やカテーテル治療、外科的治療などがあります。
梗塞の部位や重症度、栄養血管の有無、発症からの時間などを考慮して、適切な治療法が選択されます。
保存的治療では、腎梗塞の再発を予防するために抗凝固薬の投与がおこなわれます。
カテーテル治療では、薬剤を用いた血栓溶解療法や血栓除去療法などの血行再建術がおこなわれます。
外科治療には、血行再建術や腎臓摘出術などがあり、外傷により腎梗塞をきたしたケースで検討されます。
重症の腎梗塞や両側の腎臓の発症などにより急性腎不全をきたした場合には、透析治療がおこなわれることがあります。
また腎梗塞の治療と並行して、原因となった疾患の治療もおこなわれます。
腎梗塞になりやすい人・予防の方法
腎梗塞は、腎臓動脈の血流の停滞や他の臓器にできた血栓が原因で発症する場合が多い疾患です。
腎動脈瘤や大動脈瘤、大動脈解離、心房細動、心臓弁膜症、心筋梗塞、大動脈炎症候群、全身性エリテマトーデスなどの既往歴がある人は腎梗塞になりやすいと言われています。
動脈硬化も腎臓の動脈を狭窄させ、腎梗塞のリスクを高めます。
脂質異常症、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病や飲酒、喫煙の習慣、肥満症、加齢などは動脈硬化を悪化させる要因となり得ます。
原因疾患にいくつかのリスク要素が加わることで、腎梗塞を発症しやすくなると考えられます。健康的な生活習慣を心がけることは、腎梗塞の発症予防につながると言えるでしょう。
参考文献
- 両心房内巨大血栓を合併した腎梗塞の1例 日本透析医学会雑誌 49巻3号
- 腎動脈本幹の塞栓症による腎梗塞の1例 日本心臓財団 月刊心臓 42巻2号
- 症例 腎梗塞の3例 日本心臓財団 月刊心臓 26巻5号
- Ⅱ.急性腎不全 5.腎梗塞 日本内科学会雑誌 第82巻 第11号
- 2.抗血栓療法と観血的処置(循環器内科の立場より) 日本血栓止血学会誌 19巻6号
- 超音波検査で急性右腎梗塞と診断しえた急性腹症の経験 超音波検査技術 29巻1号
- 腎梗塞を契機として発見された感染性心内膜炎の1例 日本泌尿器科学会雑誌 100巻3号
- 高所転落による外傷性腎梗塞の1例 日本腹部救急医学会雑誌 29巻 7号
- e-ヘルスネット 動脈硬化
- 動脈硬化にならないためには 川崎医科大学 総合医療センター