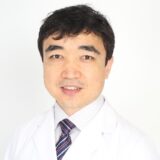監修医師:
伊藤 有毅(柏メンタルクリニック)
精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。
保有免許・資格
医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医
ADHDの概要
ADHDは注意欠如や多動症、注意欠如多動性障害とも呼ばれる発達障害の1つです。 以前は軽度発達障害という表現をされることもありましたが、障害そのものが軽度ではないことなどから、現在では用いることは少なくなってきました。
ADHDを持つ患者さんには不注意・多動性・衝動性という特徴があります。ただしこれらの性質はすべての患者さんが一様に抱えている特性ではありません。それぞれの特性のなかで顕著に出ている性質によって、不注意優位型や多動性・衝動性優位型、混合型といった表現をして細かく分類できます。
ここではそれぞれの特性について細かく見ていきましょう。
不注意
ADHDの患者さんが持つ不注意の特徴は忘れっぽく集中できないといった点があります。常にうわの空でぼんやりしてしまうだけでなく、長時間にわたって継続して1つのことに注意を向けることが苦手なケースも少なくありません。
多動性
じっとしていることが苦手という性質です。しゃべり続けてしまったり、常に手足をそわそわ動かしたりすることも多動性に含まれます。学生でよく見られる行動としては、授業中などの座っているべきタイミングで席を立ってしまうことや、過度に走り回ってしまうことが挙げられるでしょう。衝動性の特徴とも似ていることから多動・衝動性として特性をとらえることもあります。
衝動性
考える前に行動してしまう衝動性という特性を持っているため、思ったら行動にすぐ移してしまうことがあります。衝動的に行動してしまうため、ほかの人の行動をさえぎってしまうことがあります。順番を待つことが苦手なケースも少なくありません。
ADHDの原因
ADHDを持つ子どもは、脳のなかの前頭葉や線条体と呼ばれる部位でドーパミンという物質の機能障害が想定されています。また遺伝的な要因も関連しているとされています。
ADHDは発達のしかたに生まれつき周囲との差がある障害です。そのため成長とともに改善されていく課題もある点に留意しておくことが大切でしょう。
また誰しも時代背景や家庭環境、教育の環境といった外的要因を受けながら成長していくものです。発達のしかたに個人差がある場合でもこれらは同様と考えるとよいでしょう。
早い段階で気付き適切な環境のなかで成長していくことで、大人になってからのハンディキャップや生きづらさを軽減できることも少なくありません。周囲の理解やサポートが重要です。
ADHDの前兆や初期症状について
ADHDは子どもの行動にその特性が現れることで気付くケースが少なくありません。
特に物をなくしやすいことや静かに遊べないことなど、失敗と表現されてしまうことも少なくないような行動から、ADHDの可能性があるかもしれないと考える家族もいらっしゃるでしょう。進学のタイミングなどは周囲との関わりが増えるほか、同年代との比較で相対的に特性を感じることもあります。
これらの特性に気付いた場合には、主に児童精神科や小児神経科、児童科の受診が適切です。早い段階で診断を受けることで、適切な治療につなげることや、お子さんが社会生活に適合しやすい環境を構築しやすいといえるでしょう。
ADHDの検査・診断
ADHDの診断はお子さんの場合には児童精神科で、成人の場合には精神科や心療内科で医師の診察に基づいて行われます。
診断基準としては、おもにアメリカの精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)に示されており、日本の医療機関でも広く一般的に用いられます。
このDSM-5にある条件を行動の観察によって特徴から判断し、満たされたときに診断されるため、血液検査の医学的な検査数値をもとに診断するわけではありません。
具体的には不注意・多動性・衝動性の特徴が頻繁に強く認められることや、それらの症状が12歳以前より認められることを確認します。対人関係や学業や職業の面で障壁となっているかどうかも診断のうえでは重要なポイントです。
またほかの疾患にも似たような症状を引き起こすケースがあります。そのため統合失調症やほかの精神病性障害の経過中に起こるものではないことや、ほかの精神疾患ではうまく説明されないことも診断の際のポイントです。
虐待や不安定な子育て環境がお子さんの行動に影響している場合も少なくありません。医師による医学的な評価を受けることは、今後の治療方針を決めていくうえでも重要です。
家庭のなかで自己判断に頼るのではなく、不安に思う特性が見受けられるのであれば医師の診察を受けてみることをおすすめします。
ADHDの治療
ADHDを持つ子どもの治療は、環境や行動への介入と薬物療法を組み合わせて行います。症状をただ押さえ込むようなスタンスの治療方針は親子双方が問題や困難さを感じてしまうため、決してよいとはいえないでしょう。
家族や専門家、学校生活においては教師といった立場の方との連携も大切です。具体的な治療法について解説します。
環境への介入
子どもを取り巻く環境を暮らしやすいものに変えることで、本人の生きづらさを改善する方法です。例えば学校において不注意という特性に対して介入するならば、教室での机の位置や掲示物の場所を工夫することで、集中しやすくなる環境を提供するといったことが挙げられるでしょう。このような物理的な介入のほかに、勉強時間を10分〜15分単位で細かく区切ることで、長時間にわたって集中力が継続できない子どもと向き合っていく時間的な介入も考えられます。まずはお子さんの特性を正しく理解することが大切です。
行動への介入
子どもの行動のうち、好ましい行動をほめて増やしていきます。例えば静かにじっとすることが苦手なお子さんへは、いつもより長い時間を静かに過ごせたらほめるといった方法が考えられるでしょう。行動への介入で重要なポイントは、好ましくない行動に対して叱責をしないことです。先述のお子さんがじっとできていないときに叱責することは、あまりよいとはいえません。好ましくない行動に対してはできるだけ見逃すようにすることで、好ましい行動を増やそうという介入方法です。またほめると同時に、報酬としてご褒美につなげることも効果的です。報酬を得点化して、達成できたら遊園地に行くといったかたちで介入することで、好ましい行動を増やすことにつなげられると、成功体験の積み重ねにつながっていくでしょう。
薬物療法
ADHDの治療薬としてはメチルフェニデートという薬剤が、脳内の神経伝達物質の働きを調整する働きを持っていることから、ADHDの特性を軽減する可能性があるとして保険適用されています。ただしメチルフェニデートは登録された医師や専門医療機関でのみ処方が可能なため、処方が限られている点に注意が必要です。またアトモキセチンやグアンファシンといった薬剤も健康保険の適用となっています。ほかに向精神薬などを使用してADHDの特性を調整することを検討する場合もあるでしょう。これらの薬剤による効果は個人差もあるため、患者さんに合った適切な薬剤を、しっかりと時間をかけて探していくことが大切です。
ADHDになりやすい人・予防の方法
ADHDと診断される子どもの割合は、報告によって差があるものの学齢期の子どもの3〜7%程度とされています。また男女比は3.5:1程度のため、男の子の方が発達障害と診断されるケースが少なくないといえるでしょう。
なお成人してからADHDの診断を受けるケースも少なくありません。大人になってから診断を受けるケースでは、男女比の差は学齢期よりも少ないとされています。
ADHDを持つ子どもが意識的に症状を抑えることは容易ではありません。症状を押さえ込むのではなく、治療を通じて子どもの頃の発達を支援していくことが、お子さん自身の人格を形成していくうえでとても重要です。
参考文献